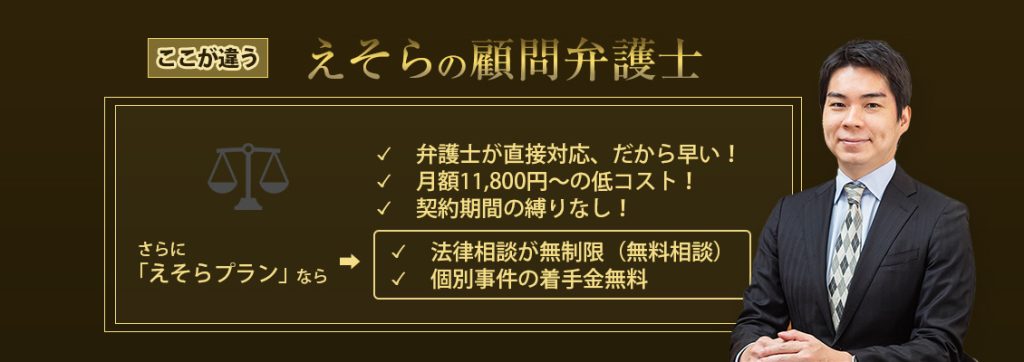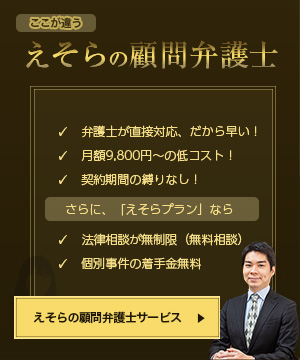1 懲戒処分とは?
(1)懲戒処分と根拠
懲戒処分とは、企業活動にとって極めて重要な職場規律・企業秩序を維持するために、服務規律や秩序違反に対する制裁として行われる不利益措置のことで、一種の秩序罰(制裁)です。懲戒処分の種類には、訓告・戒告・けん責(譴責)などの注意処分から、減給、出勤停止、懲戒休職(停職)、降格など経済的不利益を伴う処分、諭旨解雇(ゆしかいこ)・諭旨退職、懲戒解雇のように雇用契約・労働契約自体を強制的に解消する処分などがあります。
会社などの企業や組織における規律や秩序は極めて重要であると考えられることから、その中で労務を提供する従業員等の労働者は、その企業や組織の規律や秩序を守る義務を負っています。従業員がそのような義務を負う根拠=懲戒処分の法的性質については、企業の固有権であるという考え方と、契約に基づくものであるという考え方がありますが、実務的には気にする必要はありません。ただし、労働基準法89条9号は、制裁の定めをする場合においては、就業規則に「その種類及び程度に関する事項」を定めるよう求めています。
(2)懲戒権濫用法理
懲戒処分は、処分それ自体が不利益な措置であるというだけでなく、発動されれば人事考科や昇進・昇格においてもマイナスに働くことが強く想定されますし、経済的にも不利益なとなる等、従業員等の労働者にとって不利益が大きいものです。そのため、従業員等の規律違反や秩序維持違反などの問題行為があったとしても、直ちに使用者である企業や事業者が従業員に対して懲戒処分をすることが正当化されるわけではありません。
そのため、懲戒処分については、企業秩序の維持という重要な目的と労働者の不利益のバランスを取りながら積み重ねられた裁判例の解釈法理(懲戒権濫用法理)により、行き過ぎた懲戒処分(客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない懲戒処分)は使用者の権利の濫用として違法無効とされてきました。
したがって、そもそも懲戒処分を行うべきでない場合に処分した場合はもちろん、適用する懲戒処分を誤ったり(選択の誤り)、懲戒処分に至る手続に不備があったり(手続の誤り)すると、その懲戒処分は違法無効となります。場合によっては損害賠償の対象ともなるので、企業としては、降格や懲戒解雇等の特に重い処分を行う場合には、企業担当者としては顧問弁護士に相談の上で懲戒処分を実施するべきです。
なお、多数の裁判例の積み重ねの中で生まれてきた懲戒権濫用法理は、労働契約法15条で明文化されました。
(懲戒)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
2 懲戒処分の種類と基準
懲戒処分には、訓告・戒告・譴責(けんせき)、減給、出勤停止・懲戒休職(停職)、降格、諭旨解雇(諭旨退職)、懲戒解雇などがあります。これらは一般的なものであり、この他にも懲戒処分を定めることは可能で、例えば、定期昇給(ベースアップ)の昇給停止などを定めることもできます。
このように懲戒処分の種類は様々ですが、一般的には概ね次の6種類に分類できるのが普通です。処分のレベルとしては順に重くなっていきます。
訓告・戒告・譴責
いわゆる厳重注意に相当する懲戒処分です。分類としては、訓告や戒告は単に将来を戒める行為で被処分者となる従業員に何らかの行為を求めることはしませんが、譴責というのは始末書等を提出させて将来を戒める行為を言います。
いずれも、処分から直接労働者が受ける不利益はそれほど大きくないと言えますが、昇給、昇進、昇格、賞与などの人事考科で不利に考慮されることはあり得ます。
なお、譴責処分の際に始末書を出さない労働者に対して更に懲戒処分をすることができるかという点について、肯定した裁判例(東京地判昭42.11.15)もありますが、その後に否定した裁判例(高松高判昭46.2.25、大阪高判昭53.10.27)があり、現在では学説上も否定説が有力です。
減給
減給とは、労働者が実際に提供した労務の正当な対価として受け取るべき賃金を一定額減じることをいいます。
いわゆる罰金を支払わせるのに近い制裁ですが、賃金は労働者の生活にダイレクトに影響するため、労働基準法により減給の上限が定められています。具体的には、減給1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、総額が一賃金支払時期の総額の10分の1を超えることはできません(労働基準法91条)。また、複数事案であれば直ちに総額の10分の1まで減給できるのではなく、各事案ごとに減給額が平均賃金の1日分の半額を超えられないという制限があることには注意してください。
(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
労働基準法 | e-Gov法令検索
ここでいう減給1回というのは、1つの事案に対する制裁としての減給という意味です。また、賃金支払時期というのは月給制の場合には1ヶ月ということになります。
例えば、平均賃金1日分が2万円、月給が40万円の労働者に対してある1つの事案に対して減給の懲戒を行う場合、減給出来る上限額は1万円となります。この労働者が2つ以上の非違行為をしており、その複数事案の懲戒処分としての減給をする場合でも、1回の給与から減給できる総額は4万円までとなります。ただし、事項で解説する出勤停止の懲戒処分に伴い賃金が支給されない場合には、この減給の制限とは無関係です。
出勤停止・懲戒休職(停職)
出勤停止・懲戒休職(停職)とは、労働契約を存続させながら労働者の就労を一定期間禁止する制裁です。いわゆる謹慎処分です。
出勤停止期間は無給とされ(ノーワークノーペイ)、勤続年数にもカウントされないのが一般的です。
無給とされることについて、労働基準法91条の減給額の制限との関係が問題となり得ますが、行政解釈上「出勤停止期間中の賃金を受けられないことは、制裁としての出勤停止処分の当然の結果であって、通常の額以下の賃金を支給することを定める減給制裁に関する法第91条規定には関係はない」(昭23・7・3基収2177号)とされており、裁判例においても、停職に伴う手当の不支給に関し「減給の制裁に関する労働基準法91条の規定の場合とは異なる」(東京地判平9.5.22)とされています。
また、出勤停止期間に法律上の上限は設けられていませんが、1週間〜1ヶ月程度の範囲で定めていることが多いようです。出勤停止は、就労できないことそれ自体というよりは無給になるという不利益が労働者にとっては大きいことから、あまりに長い出勤停止処分の有効性は厳格に判断されるため注意が必要です。6ヶ月の懲戒休職処分について3ヶ月の限度で有効と判断した裁判例として、岩手県交通事件(盛岡地一関支部判平成8.4.17)があります。
企業としては、出勤停止処分は長くても3ヶ月程度と考えておくのが穏当であるように思われます。
降格
降格とは、役職や職位、あるいは職能資格を引き下げる処分のことをいいます。どのような降格を行うのかについては、就業規則に明示しておく必要があります。
降格には給与減額を伴うことが通常ですので、労働者にとっては長期的な経済的不利益となる重い処分です。そのため、企業や経営者としても降格処分を行う際は弁護士等の助言のもとで降格処分の法的妥当性を吟味し、しっかりとした手続を踏むべきです。
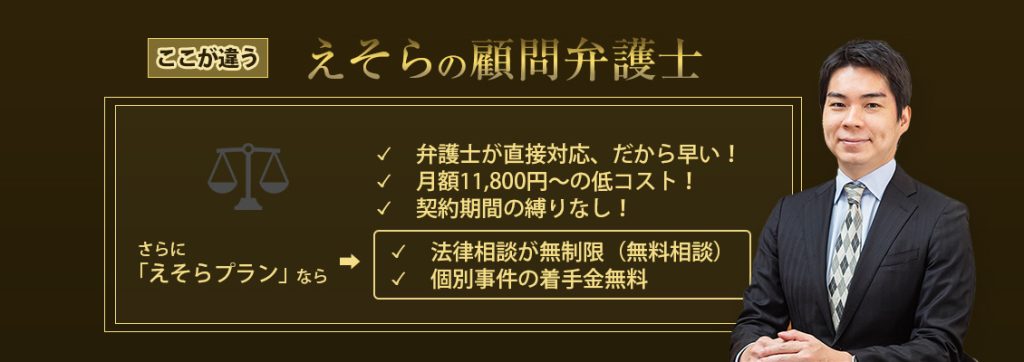
諭旨解雇(諭旨退職)
諭旨解雇(諭旨退職)とは、一定期間内に退職願の提出を勧告し、提出があれば退職扱いとし、なければ懲戒解雇とする処分です。懲戒解雇を避けられないが、最後の温情的に退職を促す措置です。
勧告に従い退職した場合には、自己都合退職として、退職金規定がある場合には規定に従い自己都合退職金を支給する例が多いです。退職金規定に、諭旨解雇の場合の退職金減額規定があれば、減額して支払うことになります。
企業としては、諭旨解雇の場合の退職金の扱いをどうするかについても予め就業規則で定めておくことが望ましいといえます。
懲戒解雇
懲戒解雇とは、労働者との労働契約・雇用契約を使用者から一方的に解約する処分であり、懲戒処分のうち最も重い処分です。最も重い処分であることから、労働者からその有効性について争われる可能性も高い処分ですので、懲戒解雇処分を行う際には必ず顧問弁護士等に相談すべきです。
懲戒解雇を行う場合、解雇予告を行わず解雇予告手当も支払わず、退職金も支給しないという扱いとなることが多いですが、これらの措置が法的に有効かについては慎重に検討する必要があります。
ア 懲戒解雇と解雇予告及び解雇予告手当
まず、解雇予告を行わず解雇予告手当も支給しないという措置については、労働基準法20条1項但書「労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合」にあたり、予告期間を設けず、解雇予告手当も支払う必要がないとされていますが、労働基準監督署の除外認定を事前に受ける必要がある点には注意が必要です(労働基準法20条3項、19条2項)。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
労働基準法 | e-Gov法令検索
イ 懲戒解雇と退職金不支給
懲戒解雇の際には退職金を支給しないという扱いについて、裁判例では、過去の労働に対する功労を全て抹消してしまうほどの、あるいは一部減殺するほどの著しい不信行為や企業秩序違反行為があった場合に限られるとして、退職金不支給の規定の有効性を限定的に解釈しています。これは、退職金が賃金の後払いとしての性格及び功労報償的性格も有しているためです。
もっとも、この場合の大前提として、懲戒解雇の場合の退職金不支給に関する規定があるということがありますので、企業側としては、実際に退職金不支給とするか否かは個別判断するとしても、退職金不支給規定自体は置いておくのがベターです。
ウ 退職後の背信行為の発覚と退職金
懲戒解雇の場合には、退職金の全部不支給や一部不支給ができる場合があるのに対して、労働者の自主退職後に懲戒解雇処分相当の背信行為が発覚した際に、退職金を不支給にしたり支払済退職金の返還を求めることができるかという問題があります。
まず、退職後に懲戒解雇相当の背信自由があることが発覚した場合に退職金の全部または一部を不支給にするという規定及び退職金返還を認める規定がない場合には、原則として退職金を不支給にするという扱いは難しいと考えられています。ただし、そのような場合でも背信性が重大な場合には、退職請求権の行使が権利濫用にあたり請求が認められないとされた事例(アイビ・プロテック事件 東京地判平12.12.18、ピアス事件 大阪地判平21.3.30)もありますので、企業としてはすぐに退職金を支払う措置を取るのではなく、退職者からの退職金請求が権利の濫用に当たるかどうかを検討する対応を取ることになります。なお、支払済の退職金の返還については、規定のない場合はかなり難しいと考えられます。
次に、退職後に懲戒解雇相当の背信自由があることが発覚した場合に退職金の全部または一部を不支給にするという規定及び退職金返還を認める規定がある場合ですが、この場合には退職金の全部または一部の不支給や、支払済退職金の返還請求も認められます。ただし、その場合でも、当該背信行為が単に懲戒解雇相当であることを超えて、過去の労働に対する功労を全て抹消してしまうほどの、あるいは一部減殺するほどの著しい不信行為があったと認められる場合に限られます。
いずれにしても、企業としては退職後に懲戒解雇相当の背信行為があった場合の退職金不支給及び退職金返還の規定を定めておくべきです。
3 懲戒処分の5つのルール
懲戒処分を行う場合の確立したルールが5つあります。①予め就業規則で懲戒事由を定めていること、②二重処罰禁止(一事不再理原則)、③処分が相当であること(比例原則)、④他事例との均衡(平等原則)、⑤適正な手続によることです。
予め就業規則に定めてあること
これは極めて重要です。懲戒処分が一種の制裁であることから、懲戒処分を科すためには、どのような行為をすれば懲戒されるのかをしっかりと事前に定めておくことが必要であり、事前に定めていない行為により懲戒処分をすることはできません。このことは最高裁判例でも確認されています(フジ興産事件 最判平15.10.10)。
そのため、企業としては予め就業規則にどのような行為がどのような懲戒処分を科されうるのかを定め、実際に懲戒処分を行う場合には就業規則に定めたどの行為に該当するのかをしっかりと検討する必要があります。
就業規則に定めのない行為に対する懲戒処分は無効となります。例えば、立川バス事件(東京高判平2.7.19)は、バスの運転手が経歴詐称で譴責処分されたものですが、裁判所は、就業規則上、経歴詐称が譴責処分の対象となっていないことを指摘して当該譴責処分を無効と判断しています。
気をつけなければいけないのは、上記事件の会社は、重要な経歴詐称については懲戒解雇処分に処すること及び情状酌量により出勤停止又は減給若しくは格下げの処分にすること自体は定めていたという点です。しかし、その定めより軽い譴責処分に処するとは書いていないことから、譴責処分をすることはできないと認定しているのです。
より軽い処分だから書いていなくても良いというわけではないというわけで、事前に対象となる行為と科されうる懲戒処分を定めておくことが極めて重要視されているということが分かります。
なお、「予め」定めておくべきという意味は、対象となる非違行為の後に就業規則に当該非違行為を懲戒事由として定めてその行為について懲戒処分をすることは認められないということです(不遡及の原則)。
二重処罰の禁止(一事不再理の原則)
1つの非違行為に対して2回以上の懲戒処分を行うことはできません。このルールは、二重処罰の禁止(一事不再理の原則)といいます。
例えば、ある非違行為を理由に出勤停止処分を受け、その後にその行為を懲戒解雇処分の理由にすることは許されません。問題社員について懲戒処分を行う場合、過去に懲戒処分の理由にした事由を今回の懲戒処分の理由に付加しないように注意してください。
二重処罰の禁止という観点からは、背信行為を調査するための期間、懲戒処分として出勤停止にするという措置を取る場合にも注意が必要です。例えば、ある従業員の横領が発覚した際に、まず出勤停止の懲戒処分に付して、その間に調査を進める等した上で、同一理由で懲戒解雇に付することはできません。このような場合には、一旦、懲戒処分としてではなく業務命令として有給での自宅待機を命じて調査を行い、適切な懲戒処分を判断すべきです。
処分の相当性(比例原則)
非違行為に対して、科される懲戒処分の重さが釣り合っていること(処分の相当性)も必要です。
例えば、宴会中のセクハラ行為を理由に支店長が懲戒解雇されたというケースで、裁判所は、セクハラ行為があったことを認定しつつも、懲戒解雇は重すぎて無効であると判断して2年分超の賃金額となる1300万円以上の賃金相当額の支払いを命じています(椿本マシナリー懲戒解雇事件 東京地判平21.4.24)。
懲戒解雇が無効になると、このように係争期間中の賃金相当額を支払わなければいけなくなるため(「バックペイ」といいます)、懲戒処分の中でも特に懲戒解雇を行う場合には顧問弁護士にも関与してもらうなど、しっかりとした対応を取る必要があります。
平等原則(平等処遇の原則)
懲戒処分をする場合、その処分が、当該企業で過去これまでに取られたことのある懲戒処分の事例に比して重すぎる等、不公平な取り扱いになっている場合には当該懲戒処分は無効になります。これを平等処遇の原則といいます。
懲戒事由として定められている行為について、これまでは大目に見てきたという会社が、いきなり同種事由を理由に特定の従業員を懲戒処分にした場合には、平等原則違反で無効とされるリスクがあります。
例えば、業務外で酒気帯び運転をして罰金刑を受けたタクシー運転手が懲戒解雇された事案で、「その対象たる非行の性質は異なるにせよ、これまで比較的寛大に懲戒権を行使してきたこと」を1つの事情として考慮して、懲戒解雇を無効とした裁判例があります(相互タクシー株式会社事件 東京高判昭59.6.20)。なお、この裁判は上告されましたが、最高裁でも結論は変わりませんでした(最判昭61.9.11)。
適正な手続を経ること
懲戒処分を恣意的に行うことは許されず、適正な手続を経て行わなければいけません。
就業規則等で懲戒手続を定めている場合には、その手続に従わないで行われた懲戒処分は無効と判断されやすいといえます。例えば、就業規則で懲戒処分を行う場合には懲戒委員会(審査委員会)を開いて審議や審査をすることになっている場合や、労働組合との事前協議をすることになっている場合などに、これらの手続を飛ばして行う懲戒処分は無効となる可能性が高いといえます。なお、公務員の場合には、交通事故等審査会や懲戒処分審査会が開かれることになっています。
適正な手続の前提は、適正な調査です。関係者からのヒアリング等、非違行為について調査をしっかりした上で、以下のような手続を履践していくことになります。なお、懲戒委員会等を設置する場合には、委員や委員の任命権者が利害関係者とならないよう注意してください。事実を調査する調査業務と問題行為を評価して懲戒処分を選択する評価業務を、調査委員会と懲罰委員会のように委員会を分けて行うということもあります。
ア 弁明の機会の付与
また、このような懲戒手続が定められていない場合であっても、対象従業員への「弁明の機会の付与」は最低限必要な手続になります。弁明の機会の付与とは、どのような問題で懲戒処分をすることを予定しているかを労働者に通知した上で、対象労働者の言い分(弁明)を聴く機会を設けることです。
弁明の機会を与えることなく行った懲戒処分は、内容自体が妥当なものであったとしても重要な手続を省略したものとして無効となりやすいので注意が必要です。
また、単に弁明書を提出させるだけでは足りず、対象労働者にしっかりとした防御の機会を与える必要があるため、どのような事実について懲戒処分を科す予定であるのかを対象労働者に具体的に通知しなければなりません。この点について、京都市北部クリーンセンター控訴事件(大阪高判平22.8.26)は、懲戒免職処分をする際には、特段の事情がない限り、対象者に対して処分の理由となる事実を具体的に告げ、弁明の機会を与えることが必要であるとして、事実が具体的に特定されていないことは問題であるとして、当該懲戒免職処分は「手続的に著しく相当性を欠く」として無効という判断をしています。
イ 書面の交付
就業規則等で定める懲戒処分手続に、懲戒処分の内容について記載した書面の交付がある場合にはこれを履践するべきなのは当然ですが、そのような規定がない場合でも、対象労働者に対してどのような理由で懲戒処分がされたのか理解させ、懲戒処分を重く受け止めさせるためにも、書面によって懲戒処分の内容と理由を通知すべきでしょう。
ウ 不服申立て
就業規則等で、懲戒処分に対して不服申立て手続を定めている場合には、対象労働者に対して不服申し立てができる旨を通知すべきです。
このような不服申し立ての手続は公務員には国家公務員法等で審査請求等が用意されていますが、民間では必ず用意しておかなければならないものではありません。しかし、裁判等の紛争に至る前に会社内で紛争解決に至る可能性のある制度ですので、特に一定規模以上の企業については導入を検討しても良いと思います。
弁護士法人えそらでは、このような制度の導入についてのサポートも行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
4 懲戒処分の選択基準
どのような非違行為に対してどのような懲戒処分を行うべきかについて、ある程度の指針がなければ、重すぎる懲戒処分として無効とされてしまうリスクがある一方で、懲戒処分が軽すぎては企業の規律維持や秩序維持という懲戒処分の目的を達成できません。そこで、ここでは、一般的にどのような行為にどのような懲戒処分を科されるのか、懲戒処分の選択基準の指針となる表を作成しましたので、ご参考にしてください。なお、懲戒処分に至らない厳重注意や訓戒といった会社としての公式な叱責という手段を経ておくということも懲戒処分の有効性を基礎付ける事実となります。
問題行為を懲戒処分以外の方法で規律するためには、会社のルールとしての服務規定や倫理規則を定めておくことや綱紀委員会を設置しておくことも有用です。
なお、下記の表はあくまで参考ですので、個別具体的事案に応じて、適切な懲戒処分を判断するようにしてください(ただし、懲戒処分を行う場合には会社や経営者が独自に判断するのではなく、顧問弁護士等への相談や助言を経るべきです。)。相談できる弁護士がいないという場合には弁護士会等に相談や紹介を求めることもご検討ください。
| 懲戒処分の種類 | 対象となる非違行為の例 |
| 訓告・戒告・譴責 | ・1日以上の無断欠勤や複数回の遅刻、サボり等 ・会社設備の私的利用 ・業務上のミスについて初めて懲戒処分を科す場合 ・継続的な勤務態度の不良 ・交通法規違反 ・細かな手続き違反 |
| 減給 | ・既に戒告処分等の減給よる軽い懲戒処分を受けているのに同種の行為を繰り返す場合 ・職員のルール違反行為のために会社に実害が生じた場合 ・軽度のセクハラ等 |
| 出勤停止 | ・重要な業務命令の拒否 ・職務放棄により会社に損害を与えた場合 ・職場内での暴力行為 ・個人情報の漏洩 ・上司への暴力や暴言 ・不適切な経理処理 ・職場外での軽度の犯罪行為 |
| 降格 | ・管理職や管理監督者の社内の重要なルールに関する違反 ・部下へのセクハラ、パワハラ等 ・意図的な背信行為で会社に実害を生じさせた場合 ・飲酒運転による物損事故等の交通事故 ・交通事故の措置義務違反 |
| 諭旨解雇・懲戒解雇 | ・着服や横領、手当等の詐取、経費の水増し精算等 ・強制わいせつ罪を構成するような重大なセクハラや、傷害罪となるような重大なパワハラ ・おおよそ14日以上の無断欠勤 ・重大な経歴詐称 ・意図的な企業秘密情報の漏洩 ・飲酒運転による人身事故 ・職場内でのトイレ等の盗撮行為 ・会社との競業行為 |
5 懲戒処分の公表
懲戒処分をしたことを社内公表することは、企業秩序の維持という観点からは重要です。他方で、懲戒対象者である職員の名誉や信用にも配慮する必要もあります。
裁判例では、従業員に不正行為等があったというりゆで懲戒解雇をした後に、名前や理由を明記して非難を含む文章を全従業員に配布して、かつ、社内に掲示したという事案で、本人の名誉・信用との関係で公表が許される範囲には限界があり、公表が適法となるのは、「公表する側にとって必要やむを得ない事情があり、必要最小限度の表現を用い、かつ被解雇者の名誉、信用を可能な限り尊重した公表方法を用いて事実をありのままに公表した場合に限られる」として会社に対して損害賠償を命じたものがあります(泉屋東京店事件 東京地判昭52.12.19)。
したがって、見せしめのような公表はもちろんのこと、安易に公表することは避けるべきです。他方で、一律に公表しないというのは萎縮しすぎですので、懲戒処分を公表したいという動機がある場合には、顧問弁護士等の意見を聴いて適切な方法と内容により公表を目指すべきでしょう。
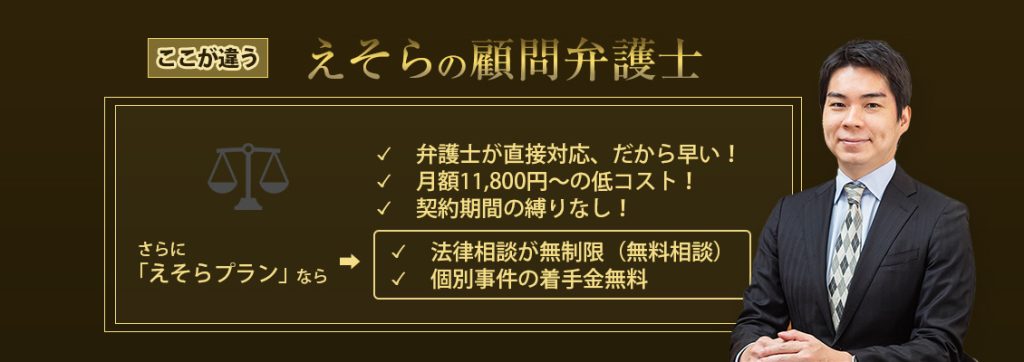
なお、懲戒対象の行為がセクハラや暴行など被害者等の利害関係者がいる場合もありますので、その場合には利害関係者に対する配慮も必要になります。
6 懲戒処分と失業保険(離職票)
会社を退職した等により失業すると、労働者は失業保険から基本手当の支給を受けられる場合があります。
普通解雇により会社を退職した離職者は、「特定受給資格者」(いわゆる会社都合退職者)として扱われ、一般の場合(自己都合退職者の場合)よりも給付日数が優遇されますが、同じ解雇であっても懲戒解雇の場合は自己の責めに帰すべき重大な理由によるものとされ(離職票上の重責解雇)、この優遇を受けられません。他方で、戒告や減給等の懲戒処分は失業保険の給付に影響することはなく、それらの懲戒処分を受けた労働者が後に退職した場合には、その退職理由に応じて、自己都合か会社都合か判断されることになります。
なお、懲戒解雇や諭旨解雇処分を受けて退職した労働者は、転職活動の際に前職での処分歴の申告義務があると考えられており、前職での懲戒解雇歴を隠して就職したことが解雇理由になるとした裁判例(名古屋高判昭51.12.23等)もあるので、懲戒解雇処分や諭旨解雇処分は労働者にとっては単に職を失うこと以上の不利益がある処分となります。他方で、降格以下の懲戒処分については申告義務まではないと考えられています。
7 懲戒処分の前に弁護士に相談しよう
以上見てきたように、懲戒処分は、企業秩序の維持のために必要不可欠なものではあるものの、安易に懲戒処分の措置を取ってしまうと、労働者から事後的に争われて無効となってしまうことがあります。無効となるということは、労働者からの損害賠償や賃金請求が認められるリスクがあるということですから、会社としてもしっかりと懲戒処分について有効となるように事実を調査し、科すべき処分を検討し、適正な手続きを履践して行うことが必要です。
そのためには、労働法務に精通した弁護士のサポートが必須であると言えますので、懲戒処分の際には、経営者や人事部などの一存で進めるのではなく、必ず弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士法人えそらでは懲戒処分の際の相談や助言その他のサポートを受けておりますので、ご希望の場合にはお気軽にお問い合わせください。